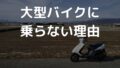二輪教習の難関課題の一つ、「急制動」。教習中は「急ブレーキ」という意識が強くありませんでしたか? でも、実際に公道を走ってみると、あの感覚は「信号が黄色になったので少し強めにブレーキを踏んで止まる」くらいに近いんです。むしろ「急制動」という名前が誤解を生みやすく、「目標位置でしっかり止まる練習」と言った方がしっくりくる気がします。「急制動」という名前が精神的なプレッシャーになり難易度を上げていると感じています。
「急ブレーキ」を意識しすぎると、タイヤがロックして卒検では一発失格、最悪の場合は転倒につながる危険もあります。実は、焦って急ブレーキをかけなくても、規定の距離手前で十分に止まれるんです。
私の場合は、逆にブレーキが強すぎてかなり手前で止まってしまい、教官から「タイヤロックするから、もっとブレーキは弱めに」と何度も注意されました。それでも「急ブレーキ」のイメージが抜けず、MTの検定では見事にタイヤをロックさせて不合格…という苦い経験があります。
急制動で本当に重要なのは「加速」だった!速度不足は失敗のもと
「急制動」というとブレーキ操作に意識が向きがちですが、卒検で失敗した私が痛感したのは、実はブレーキよりも「加速」が重要だということ。 なぜなら、ブレーキ開始地点に「40キロで進入する」必要があるからです。
ブレーキ地点ぴったりで40キロになるように加速しながら調整するのは、想像以上に難易度が高いです。まず、40キロぴったりで進入すること自体が至難の業。仮にできたとしても、加速しながらブレーキングポイントを迎えると、フロントフォークが大きく沈み込む「ノーズダイブ」が発生しやすくなり、車体が非常に不安定になります。
実際に私は、大型二輪の卒検で加速が足りず(速度不足で)焦ってしまい、急ブレーキと激しいノーズダイブでタイヤをロックさせ停止した瞬間に転倒、もちろん失格となりました。加速が緩慢だったため、ブレーキ地点の手前でまだ加速している最中だったのです。
【急制動のコツ①】安定進入の鍵は「アクセルオフ」
では、どうすれば安定して40キロでブレーキ地点に入れるのでしょうか? そのコツは「アクセルオフ」で進入することです。
ブレーキ地点のバイク2~3台分手前で45キロ程度までしっかり加速し、その後アクセルを完全に戻して(アクセルオフ)、惰性でブレーキ地点に進入します。 こうすることで、40~42キロ程度の適切な速度で、しかも安定した状態でブレーキを開始できます。
加速しながら40キロに合わせるよりも、少し速い速度から減速して40キロに合わせる方が圧倒的に簡単ですし、加速していないためノーズダイブも最小限に抑えられ、車体が安定します。だからこそ、ブレーキ地点までの「加速」が重要なんです。卒検の補習では、この「手前で45キロまで加速する練習」を集中的に行い、ようやく安定して急制動をクリアできるようになりました。
【急制動のコツ②】40キロ出ない?加速不足の原因と対策(シフトアップが早すぎ)
私が加速不足(速度不足)に陥っていた原因は、1速から2速へのシフトアップが早すぎたことでした。エンジンの回転数を上げて加速するのが好きではなかったため、無意識のうちに超低速で2速に入れていたのです(1速で少し動き出したらすぐに2速へ、という感じ)。大型バイクは低回転でもトルクがあるので、それでも普通に走れてしまい後々、急制動の加速が緩慢になることに。
教習所内はほとんど2速で走行可能で、外周でたまに3速に入れる程度。1速は停止から発進して数mだけでした。普段は早めのシフトアップでも問題ありませんが、急制動の加速時だけは別です。 しっかり加速するためには、1速である程度エンジン回転数を上げてから2速にシフトアップする必要があります。特に私のように小型や普通のAT限定免許(スクーター)の経験しかないと、アクセルを回すだけで加速できていたため、MT車の適切な加速タイミングに戸惑うことがあります。教官に指摘されるまで、自分のシフトアップが早すぎること(2速のままゆっくり加速していること)に全く気づきませんでした。
もし「急制動で40キロまで速度が出ない」と悩んでいるなら、一度シフトアップのタイミングを見直してみてください。1速でしっかり引っ張る意識を持つだけで、加速は見違えるようにスムーズになります。
【急制動のコツ③】タイヤロックを防ぐブレーキ操作のやり方
適切な速度で進入できたら、次はブレーキ操作です。よく言われる理想のブレーキ配分は「前輪:後輪=7:3」。フロントブレーキ主体で考えるのが基本です。ただし、フロントブレーキだけではロックや転倒のリスクが高まりますし、リアブレーキ主体では制動距離が伸びてしまい、「止まれない」原因になるし、リアタイヤはフロントよりロックしやすいです。もちろん、バイクの種類によっては理想のブレーキ配分は変わってきますが、教習所のバイクはフロントブレーキ主体で考えるのが基本。
ブレーキの握り方のイメージは、「最初は軽く握り、徐々に力を込めてギュギュッと握り込む」感じです。決して、最初からガツンと100%の力で握らないでください。これがタイヤロックの最大の原因です。私が卒検でロックさせてしまったのも、焦りから一気にブレーキを握りしめてしまったためでした。
前後輪のブレーキをバランス良く、かつ段階的にかけていくことで、タイヤをロックさせることなく、目標位置でスムーズに停止できます。視線は目標地点の少し先を見ると、バランスも取りやすくなりますよ。何度も書きますが、急制動は急ブレーキではなくて、「目標位置で止まる練習」です。
まとめ:急制動は加速が9割!苦手意識を克服して卒検合格へ
二輪教習の急制動は、「急ブレーキ」という名前のイメージに惑わされず、「①適切な加速 → ②アクセルオフで安定進入 → ③段階的なブレーキ」という一連の流れで捉えることが重要です。特に、ブレーキ開始地点までの加速(とアクセルオフ)が成功の鍵を握っています。
もしあなたが急制動が苦手だったり、速度不足で悩んでいたり、卒検で失敗してしまったりした経験があるなら、ぜひ「加速」の練習と「アクセルオフ進入」を意識してみてください。この記事のコツが、あなたの苦手克服と卒検合格の一助となれば幸いです!